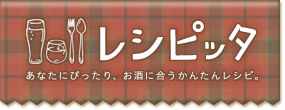保存性だけじゃなかった!缶詰は買ってよし、食べてよしの優等生!!コラム
vol.37
2014年4月23日
すっかり生活に溶け込んでいる感のある缶詰は、19世紀初頭、戦争の遠征先で兵士たちの食糧問題に悩んでいたフランスの皇帝・ナポレオンが、新鮮で美味しいまま食料を長期保存できる方法を模索し、その発明に懸賞金をかけたことが始まりでした。フランス人のニコラ・アペールが、ガラス瓶に食品を入れ、コルク栓で蓋をして加熱して脱気し、ロウで密封するという現在の缶詰の元になる加工方法を発明して懸賞金を得、その製法を各国の言葉で出版したそうです。そのすぐ後、イギリスでピーター・デュラントがブリキの缶に食品を詰めて密閉する方法を発案し、缶詰工場を造ったのです。しかし当時の缶詰は完全に手作業で作られていたため高価で、ほとんど軍や冒険家などの使用に限られていました。それから缶の素材や密閉方法に様々な工夫が施され、開拓民とともにアメリカへ渡ると、その長期保存性が買われて爆発的に生産が伸びました。
そんな缶詰が日本に渡ってきたのは明治4年(1871)。長崎でフランス人がいわしの油漬けの製法を伝えました。その後、明治明治10年(1877年)に北海道でさけの缶詰が工場にて生産されるようになって全国に広まって行ったそうです。
ここ最近は“缶つま”などのブームや、非常食として買い置いた缶詰を入れ替える時になどに、缶詰を食べる機会もあるのでは。そんな時、ただ缶を開けたまま食べるのは味気ないですよね。そこで、料理研究家で管理栄養士の杉山文(すぎやまあや)さんに缶詰の美味しい食べ方を聞いてみました。
「缶詰のいいところは、開ければすぐに使えるところです。それに、買い置きをしておける。それから、缶の旨みは固形分だけでなく、缶汁にも含まれているので、丸ごと全部使えて、捨てるところがないほどのスグレものなのです。例えばいわしだと、オイルサーディンを使えば、いわしを処理する手間がいらず、ゴミも出ません。そして何より嬉しいのは、骨まで柔らかいので骨ごと食べられて、カルシウムもたっぷりと摂れるという点です。ほたて貝柱の缶詰など、缶汁ごとつかえるメニューでない場合、缶汁だけを煮物のダシとして使ったり、卵焼きに加えたりすると、いつもの料理が1ランクもツーランクも上のものに仕上がるんですよ」と杉山先生は話します。実際、缶詰の魚や肉はすでに食べられる状態になっているので、捨てるのは缶だけ。ではどんな風に使うのに適しているのでしょうか「そのままでも勿論いいのですが、缶詰は独特の匂いがあり、それをカバーするために、私はよくパスタやスープ、ソース、煮物などの材料のひとつとして使います。例えば、ツナ缶の炊き込みご飯を作る時、塩昆布で旨みを足して、仕上げにスクランブルエッグを混ぜ込んで香ばしさと色味を足します。トマト缶なら、そのまま使うのではなく、沢山の玉ねぎとにんにくを焦がさずによく炒めたところに加えて5分ほど煮ることで、驚くほど深い味わいのソースになるのです。ピザやパスタ、煮込み料理に使って自家製ソースだと言えば、ばれないかもしれませんね。面倒そうでも、一度に沢山作って冷凍しておくと、必要な時にすぐ使えて便利なんです」。杉山先生の話ではひと手間加えることで、缶詰が極上の味に変わるようです。「缶詰は、それだけでなく何かといっしょに調理することで、その美味しさが二倍、三倍になるので、色々と試してみてください」。
では、杉山先生は、どんな缶詰を常備しているのでしょうか。「私が普段買い置きをしているのは、素材系が多いですね。前述したトマト缶や、ホタテ貝柱缶、ツナ缶、コーンクリーム缶、ホワイトソースの缶詰やデミグラスソースなども置いています。あと欠かせないのがマッシュルーム缶です。これを加えるだけでグッと高級感が増します。もし残っても、冷凍して早めに使えばOKですよ。それから、缶詰のいい点は、季節を問わずにいつでも使えるところと、価格が安定しているというところもあります」。なるほど、缶詰には味や使いやすさだけではなく、色んな長所もあるようです。今回の特集を機会に、皆さんもぜひ新しい缶詰料理にチャレンジしてみてください!