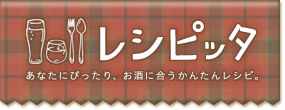�g�̂ɂ����������^�b�v���I���{�l�͐��E�ōł��������D���I�H�R����
vol.29
2012�N10��15��

�@�����Ƃ����A���ꂼ��̑��̖{���͒m���Ă��܂���ˁB���R�Ȃ���A������8�{�A������10�{�B�����Ƃ����͐e�ʂɓ�����A�����͂��̑��̖{������\�r�ڂƂ�����ނɕ��ނ���܂��B�����͐H�p�̂��̂����H�p�̂��̂܂Ŕ��Ɏ�ނ������A���{�ߊC�����ł�100��ވȏオ�������Ă��܂��B���̕��z�͈��M�т��犦�т܂łƕ��L���A�C����[�C�܂Ő��E���̊C�ɂ���A�̒�2�p�`20���܂łƃT�C�Y���o���G�e�B�ɕx��ł��܂��B
�@���̒��ŐH�p�Ƃ���Ă��� ���̂�80�����X�����C�J�ŁA���{�S���̉��݂ɕ��z���Ă��܂��B�X�����C�J�̓����C�J�ɔ�ׂ�ƁA����^�Őg�������A�R�N�̂���Â݂�L���Ă��܂��B�{�͉āA�~�̗����̐�������܂����A���̂Ƃ���͂�����Ƃ������Ƃ͕�����܂���B�Ƃ����̂��A�����͋ؓ��Ɏ��b��~�ς��Ȃ��̂ŁA���b�̑����ɂ��{���v��ɂ����̂ł��B���̂��A�ŁA��N��ʂ��Ă��܂�傫�Ȗ��̍��������Ȃ��悤�ł��B
�@�P���T�L�C�J�́u�G���̉��l�v�ƌĂ��ō����i�ŁA�����Ń����C�J�A�X�����C�J�ƃ����N�t������Ă��܂��B���̖����A�����C�J�A�X�����C�J���˂��Ƃ�Ƃ����������Ȃ̂ɑ��āA�P���T�L�C�J�̓R���R���Ƃ����Ɠ��̎�����������܂��B���ɂ��A�x�R�p�̖��Y�̃z�^���C�J�͔����������������Ȃ����ŁA�V�[�Y���̖�͊C�ʂ��Q�V���A���t�̖ԂɐG��Ĕ�������l�͏t�̕������Ƃ��č��̓��ʓV�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B����ɁA�T�̂悤�ȍb����̓��Ɏ��R�E�C�J��A�������g���������S�E�C�J�A�Ⓚ�Ń��[���C�J�Ƃ��Ĕ����Ă��郈�[���b�p�R�E�C�J�Ȃǂ��L���Ȏ�ނł��B
�@�����͐̂���悭�����������Ȃǂƌ�����̂ł����A���͋��̏������ԂƑ卷�͂Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B�����̎|�݂̎听���́A�A�~�m�_��������^�E�����ƃx�^�C���Ń^�E�����͉h�{�h�����N��T�v�������g�Ȃǂ���������Ă��܂��ˁB��J�A�����̒����A�����R���X�e���[���̌����A�S���̋����A�n���̗\�h�A�̑��̉�ō�p���T�|�[�g������A�s�����̉��P�A�C���X�����̕���𑣐i�����A�a��\�h����A�Ƃ������������m�F����Ă��܂��B�Ԗ��ɂ̓^�E��������������܂܂�邱�Ƃ���A�ᐸ��J�̗\�h�E�̍�p���m�F����Ă��܂��B�ڂ̌��N����K���a�̗\�h�ȂǁA���̎���ɂƂĂ��L�p�Ȑ����Ȃ̂ł��B
�@�����̎|�݂́A���ƈ���Ē��߂���̏n���ɂ���đ������邱�Ƃ��Ȃ��̂ŁA�V�N�Ȃقǔ��������Ƃ����܂��B�ł́A���̔����������ő�ɖ��키�ɂ͂ǂ���������ł��傤���B
�h�g�ŐH����ꍇ�A���i�͓����ɂ���悤�ɐ��Ă��܂��B�����Ɠ��̎��������y���݂������́A�����̓����c�������炢�̒����ɐ�A���ɓ����c�ɐ�悤�ɍׂ����Ă����܂��B�����c�����ɍׂ���ƍ��܂łƂ͈ꖡ�Ⴄ�������悭�A���������h�g�����킦��̂ł��B
�@�ł́A���������M���鎞�͂ǂ���������ł��傤���B�����͔M��������ƃN�����Ɗۂ܂��Ă��܂��܂���ˁB����́A�����̓��ɂ���炪�M�ɂ���ďk��ł��܂����ƂŋN����܂��B�����̕\�ʂɂ�4�w�̔炪����A�����Ŕ�����̂͂��̂�����2�w�����B�������Ɏc��2�w�����M�ɂ���ďk�ނ̂ł��B�����ʼn��M���鎞�ɁA�\�ʂɎ��̎q�i�ߏ\�����̐荞�݁j�����A���ʂɏc�̋�����ƁA�ۂ܂炸�ɉ��M�ł��܂��B�܂��A�t�ɂ��̊ۂ܂鐫���𗘗p���āA�\�ʂɎ��̎q�����A���ʂɂ͉�����ڂ����Ȃ��ƁA�N�����Ɠ����Ɋۂ܂��āA���̎q�̐�ڂ����ꂢ�ɊJ�����C�J����邱�Ƃ��ł���̂ł��B�A���A�C������_���ЂƂ�������܂��B���������M����60������ƁA�g���ǂ�ǂ�d�����܂��Ă��܂��܂��B�ł�������M���n�߂Ă����̐g���ӂ�����Ƃ��Ă����ȂƎv������A���M����߂邩�A��U�������������o���̂������ł��傤�B�����đ��̑f�ނɉ�ʂ��čŌ�ɂ������Ăщ����ĂȂ��܂��܂��B
�@�ۂ̂܂܂̂�������ɓ��������̉������炦���Љ�܂��B�܂��Q�\�Ɠ��̊Ԃ��瓷�̒��Ɏw�����A���Ɠ����q�����Ă��镔�����O���܂��B���̎��������肷����Ɩn�܂�^�i�����j���j�ꂽ�肷��̂ŁA�������Ă���ꏊ������̌��ԂɎw�����A���Ɍ������Ċ��点��悤�ɂ���Ɨ͂����炸�ɊO���܂��B�����ē����Ɏc�����ג���������������A�悭�����܂��B��ɂ��Ďg��Ȃ��ꍇ�́A���Ƒ��̋��ڂ�����������ɓ���A�������Ɍ������Ă����Ɠ��̐�J���ƁA���^������ȒP�Ɏ�邱�Ƃ��ł��܂��B���C����������悤�ɐ@���������A�G���y���i�݂݁j����O���A�������肪����ɔ���܂��B�炪�����Č����ɂ����̂Ńy�[�p�[�^�I���ȂǂŔ���܂ނƂ����ł��傤�B�Q�\(���̕���)�͖ڂƓ����̊Ԃɕ�����Đ藣���A�Q�\�̖ڂƖڂ̊Ԃ��J���ĉG��(���炷�����E��)�Ɩڂ����܂��傤�B�Q�\���������Ƌz�Ղ̒����珬�����ۂ��ւ������o�Ă���̂ŁA�傫�����̂��o�Ȃ��Ȃ�܂ł������Đ��Ő܂��B���C������đ��̐���ق�̏�����A�����𑵂��܂��B2�{����������������A���̑��Ƃ�������ɂ��܂��B
�@�����܂łł������̓��V�s�ɂ����āB�����Ɏg��Ȃ����̓��b�v�ŋ�C������Ȃ��悤�ɕ��ŁA�Ⓚ�ɂցB���Ɛ��̗Ⓚ�Ȃ̂�1�T�Ԃ��߂ǂɎg���Ă��������B���āA���̉𓀕��@�ł����A�����͂ǂ�ȉ𓀂����Ă����͂���܂薡�̕ς��Ȃ��̂ł��B������}���̎��͑܂��Ɨ����𓀂ł��A�������܂ܓ�ɓ������ł��܂��B
�@�Ō�ɐV�N�Ȃ����̌����������B�����͊l��Ă��玞�Ԃ̌o�߂ƂƂ��Ɂu�F������v�Ƃ����A���x���F���ς�����茳�ɖ߂����肷�錻�ۂ��N�����܂��B�Ⴆ�X�����C�J�́A�C����g�������ɂ́A�������ĕp�ɂɐF��ς��Ă��܂����A20�����炢��ɂ͂��������Ȃ�܂��B ���̎��Ƀg�����ɋl�߂���A�Ⓚ�����肵�Ă��܂��ƁA�����F���蒅���܂��B ��40����ɂ͌���Ɠ������̂��钃���F�ɂȂ�܂��B�①�ۊǂ��Ă��鎞�ɕX��������ƁA�����͔����Ȃ��Ă��܂��܂��B�①��Ԃł���Δ����`1���őN�x��������ƁA�Ăѕs�����ȓ����F�ɂȂ�A�①�Ŋl���2���قǂ��������͓̂������̂Ȃ��Ԃ��ۂ��F�ɂȂ�܂��B�ŋ߂͑D��Œ����F�ɌŒ肳����Z�p��A���Z�p�̐i���ŁA�s��̃X�[�p�[�ł��l���40����̂悤�Ȍ���̂��钃���F�̂����������Ă��܂��B�F�ȊO�̃`�F�b�N�|�C���g�́A���ɒ��肪�����Đ^��������ł��Ȃ����̂��V�N�ȏؖ��ł��B
�@���āA����͂���Ȃ����Ɏv����y���A�C�G���[�G�v�����Y�̃��V�s�ňꌣ�A�������ł����B